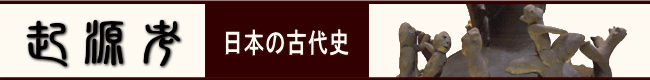目子媛の「草香」―1
はじめに
継体天皇の元妃は尾張連草香女、目子媛とされ、この妃の皇子が安閑天皇・宣化天皇となり皇統を継いでいる。本論は草香目子媛の草香が草香部氏を表すという議論である。
ただこれを説明するには五世紀の王権の性格から述べなければならない。五世紀の政治過程は東漢氏が台頭し権力を握っていくプロセスであり、一方で草香部氏をはじめとする難波吉士が淀川を遡上し近江から尾張へと侵攻していくプロセスでもある。雄略以降の政治過程の実態は東漢氏と草香部の両頭政治であるというのが本論の骨子である。
倭の五王
倭の五王をどのように比定するかは、いろいろと議論があり、通説とよばれるものはないのが現状である。五世紀の倭王を中国史書は五人記すのに対し『記紀』は七人である。私は五世紀の倭王は五人であり、『記紀』の書く七人のうち二人は存在が疑わしいと考える。
倭の五王が誰かに答えるには、王権を支える勢力がどう変遷したかを見る必要がある。まず、
応神→ 仁徳→ 履中
という推移において履中朝に変化がある。履中はイサホワケと言った。イサホというのは
イ(接頭辞) + サホ(狭穂)
という名である。「イ久米入彦イ幸」のようにイは接頭語として盛んに用いられている。
サホは、佐保川流域、垂仁皇后狭穂姫以来の地であり、和珥氏物部氏らの勢力が存在した地域である。和珥氏は近江から山背、盆地東北部まで所在した勢力と考えられている。履中は住吉仲皇子の乱を避けて石上神宮に入るが、名前からしてもともと石上に近い人物である。王名にサホという地域名が入っていることは、その地域の勢力との繋がりが深いものとみなければならない。
履中は住吉仲皇子を討って即位する。住吉仲皇子を討つことを進言する三人(履中の擁立者)と、履中の国政に参画したという四人は次のようである。
(擁立者) 平群氏・物部氏・阿知使主
(国政に参画) 平群氏・物部氏・蘇我満知・円大使主
履中擁立の三人と国政に参画した四人は対応し、漢直の祖阿知使主=蘇我満知だと思うが、この点は後述する。
円大使主とは葛城氏であるが、住吉仲皇子を討つのに葛城氏が加わっていないのは、住吉仲皇子が葛城系の皇子だからだろう。葛城系の人物が排されサホ(盆地北東部の和珥物部氏)系の王が立ったというのが履中なわけである。
葛城氏とサホ勢力の抗争は、すでに仁徳朝で見ることができる。仁徳の皇后ははじめ葛城磐之媛であったが、その後、八田皇后となる。八田皇女は『紀』では菟道稚郎子皇子が遺言で進上した人物となっており、和珥氏からの入妃である。八田は盆地北部の矢田丘陵のヤタであり、ここは物部氏の支配が認められる地域でもある。
八田皇后が立ったということは、王権の中でサホ勢力が葛城氏を押さえて主導的な地位を占めたことを意味する。磐之媛の嫉妬というのは、八田皇后が立つに際しての葛城氏の抵抗を表すものであろう。『記紀』では磐之媛の没後、八田皇后が立ったことになっているが、実際没後だったかは疑問で、問題は皇妃の交替があったということであり、それは王権の背後勢力の交替を意味するわけである。
さて、住吉仲皇子の乱が「サホ―葛城」の抗争を意味するものであるとすれば、瑞歯別が王位に就くのは難しいと言えよう。瑞歯別は住吉仲皇子と通じていないことを証するために仲皇子を殺害する。つまり瑞歯別は兄を殺して、葛城系の立場に立たないことを証したわけだが、それは本来葛城系の人物であったからである。葛城氏を排してサホの王が立つという政治的な流れの中で河内丹比の葛城系と思われる人物が王位につく暇はありそうにない。まず反正天皇を除かなければならない。
*
もう一つ、『書紀』の物語で造作性が高いのは、眉輪王の安康殺害から雄略が立つという物語である。この時、大泊瀬皇子が眉輪王を匿った葛城氏を討っている。この一連の物語をそのまま信じるというわけにはいかない。
後の山背大兄王と田村皇子の王位を巡る争いなどから覗われるように、王位に就くには諸臣の意向が重視された。その点から言えば、即位前の一人の皇子が葛城氏を討つだけの権限を発揮できたとは思えないし、軍事力という点でも、葛城氏に勝るものが用意できたとは思えない。ただ後に葛城氏が雄略に討たれるのは事実のようだが、それは雄略即位後の話である。
では安康殺害譚とは何か。『書紀』の安康紀は安康の事跡はほとんどなく、次の三つの話によって構成されている。
○木梨軽皇子が暴虐をふるい、婦女への淫行に及んだために群臣が従わず、自害する。
○大草香皇子は、妹の幡梭皇女に対する大泊瀬皇子の求婚を承諾したが、仲介した根使主の讒言によって、殺される。
○安康(穴穂皇子)が眉輪王に殺される(その前段の話)。
ここで木梨軽皇子だが、
オシサカ(忍坂)大中姫 ― 軽皇子
という系譜は、
オシサカ(押坂)彦人大兄皇子 ― 軽皇子(孝徳)
という系譜と類似する。木梨軽皇子というのはオシサカ氏であろう。そのオシサカ氏の皇子が自害した。
また大草香皇子は允恭即位の時にも天皇候補に名があがっており有力な皇位継承者であった。その人物が殺された。
安康は穴穂皇子であり、石上穴穂、つまり物部氏を背後勢力として持つ人物である。その人物も殺される。
つまり、『書紀』の安康紀は、オシサカ氏、草香部氏、物部氏という三人の有力な皇位継承者がことごとく排されるという物語である。排される理由が、婦女淫行だとか、珠蔓を横領した人物による讒言だとか、七歳の子どもによる殺害だとかいうのは、いずれも創作話とみた方がよい。
ただ当時の有力な皇位継承者がオシサカ氏、草香部氏、物部氏であり、それらの皇子が排されて雄略が王位に就くという点では真実を伝えているのではなかろうか。要するに、安康は石上にいた皇子をあらわしてはいるが、天皇とみることはできないということである。
東漢氏の台頭
以上に述べてきたように、七人の王の中から反正と安康の二人を除くべきというのが私の考えである。結局倭の五王は、次のようになる。
応神→ 仁徳→ 履中→ 允恭→ 雄略
五世紀の王をこのように考えると、この王権の推移の背後で、一つの勢力が台頭しているのを見ることができる。その勢力とは東漢氏である。
応神十五年 百済王、阿直岐を派遣して良馬二頭を献上。
応神二十年 倭漢直の祖阿知使主、十七県の党類を率いて来朝。
阿直岐(『記』は阿知吉師)のキは吉士の意のようである。
すると十五年の来倭の人物も二十年の来倭の人物も、どちらもアチという名である。これは同一人物であろう。十七県もの党類を率いていきなりやって来るというのは無謀で、十五年の時に下見をし準備をした上で、二十年に来倭したものとみてよいだろう。
阿知使主は応神朝に来倭し、仁徳朝(珍とみておよそ十年ほど)を経て、次の履中を立てる時には住吉仲皇子を討って活躍しているわけである。住吉仲皇子を討つ人物として『書紀』は、平群・物部・阿知の三人をあげるが、『記』は阿知直一人の活躍として描き、政変の後には「天皇、ここに阿知直を以て、始めて蔵官に任じ田地を与えた」としている。東漢氏が国政の重職についたのである。
当時、渡来人はふつう臣・連の下に編成され、使役される存在だった。しかし、阿知使主は倭王の擁立にまで関与している。なぜそのような立場をとりえたのか。応神十五年の時にはアチは百済王の遣いである。するとアチは百済王の臣に違いなく、百済の臣という立場で、倭の政権に参画し権勢を発揮したのであろう。百済からすれば良馬を贈り、臣下を派遣して倭王権に食い入ったわけである。
雄略朝では東漢氏は王権の中枢にいる。『書紀』によれば、雄略は臨終にあたって、大伴室屋大連、東漢掬直に遺詔したという。掬は阿知使主の子である。また雄略が愛寵した人物は、檜隈民使博徳、身狭村主青の二人だったというが、檜隈は東漢氏が応神より与えられて住んだ土地であり、身狭も、檜隈の入り口にある土地である。檜隈の人、つまり東漢氏が雄略王権を動かしているのである。
では、履中と雄略の間に入る允恭はどうだろうか。允恭は雄朝津間稚子宿禰だが、朝津間というのは葛城の地である。履中を擁立したのはサホ勢力だと述べたが、では再び葛城氏へと勢力が移ったのだろうか。また允恭の時には新羅から医者が来たり、崩御時にも新羅から大きな弔問があったと書紀は記しており、允恭は新羅との関係が深い天皇のように見える。
しかし、葛城朝津間という土地は、南郷遺跡群に隣接する地域である。南郷遺跡は五世紀の第二四半期を中心に営まれ、金属・ガラス・鹿角などの工房を含む大規模な渡来系の集落跡である。ここからは大量の韓式土器が出土しているが、その土器は百済系のものである。つまり雄朝津間稚子宿禰(允恭)は、葛城の土地から立った王ではあるが、その実質的な擁立勢力は百済系渡来人であり、阿知使主を首長とする東漢氏であったということである。
葛城韓媛は、葛城氏が雄略に贖罪として入れた姫だとされている。しかし葛城氏は、
允恭 葛城玉田宿禰が討たれる
雄略 葛城円大臣が討たれる
という形で二代に渡って勢力が削がれている。葛城氏は雄略朝頃没落したと見てよい。しかし葛城韓媛の子が清寧(白髪皇子)であり、清寧が皇位についてからは皇太夫人と呼ばれたとされている。皇妃は政治的存在と見るべきである。葛城氏が没落した後、葛城氏が入れた妃が王権の中で力を発揮するというようなことは普通はありえない。
韓媛という名は韓人の姫ということであり、渡来の姫と解される。韓媛は、実質的には渡来人である東漢氏が入れた姫と理解すべきであろう。
当時の皇妃は、大臣と擬制的に親族関係を結んだ後に入れられたのではないかと思う。昨年NHKの大河ドラマで放送された篤姫でも、篤姫は島津本家の養女となり、徳川家に嫁ぐにあたっては近衛家の娘となっている。同様なことが古くからあったのではないか。
履中妃の黒媛を『記』は葛城葦田宿禰の女とし、『紀』は羽田八代宿禰の女としているのも、実際には羽田八代宿禰の女なのであるが、羽田氏という渡来人を束ね、大臣の職にあった葛城氏の名をもって皇妃として入れられたということであろう。
東漢氏は来倭後、まず葛城氏の地域に入り葛城氏のもとに編成されたものと考えられる。それが、履中朝になると王権の擁立に参画すると共に、前述した黒媛(東漢氏系渡来人の女)を葛城氏の名で皇妃に入れる。允恭朝でもなお葛城氏の名をもって王権を擁立するが、雄略朝では葛城氏を完全に排除した王権を立てるに至るわけである。
先に述べたように、履中の擁立者三人と履中朝の国政に参画した四人が対応するとみると、
漢直の祖阿知使主 = 蘇我満知宿禰
ということになる。蘇我氏の出自については諸説あり、中には新興氏族とする見解がある。蘇我氏は東漢氏の上に立っている氏族であるが、東漢氏は雄略朝では王権の中枢にいる氏族である。新興氏族がひょっこり現れ、王権中枢にいる氏族の上に立てるわけはないだろう。蘇我氏は漢直の祖阿知使主の後裔氏族であり、東漢氏の首長層と見てよく、阿知使主に対応する位置に蘇我満知という名があらわれるというのがむしろ自然なのである。
蘇我氏は、推古朝で葛城を自分の本居の地として返還を主張しているが、これは一つには、蘇我氏が韓媛を葛城氏の名で入れて葛城氏と結びついた氏族であるということと共に、允恭を擁立した南郷遺跡群周辺に住んだ百済人を同族とする氏族であるということを示すものと解される。
(次ページ)